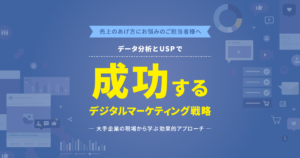新規事業開発のプロトタイプの重要性について
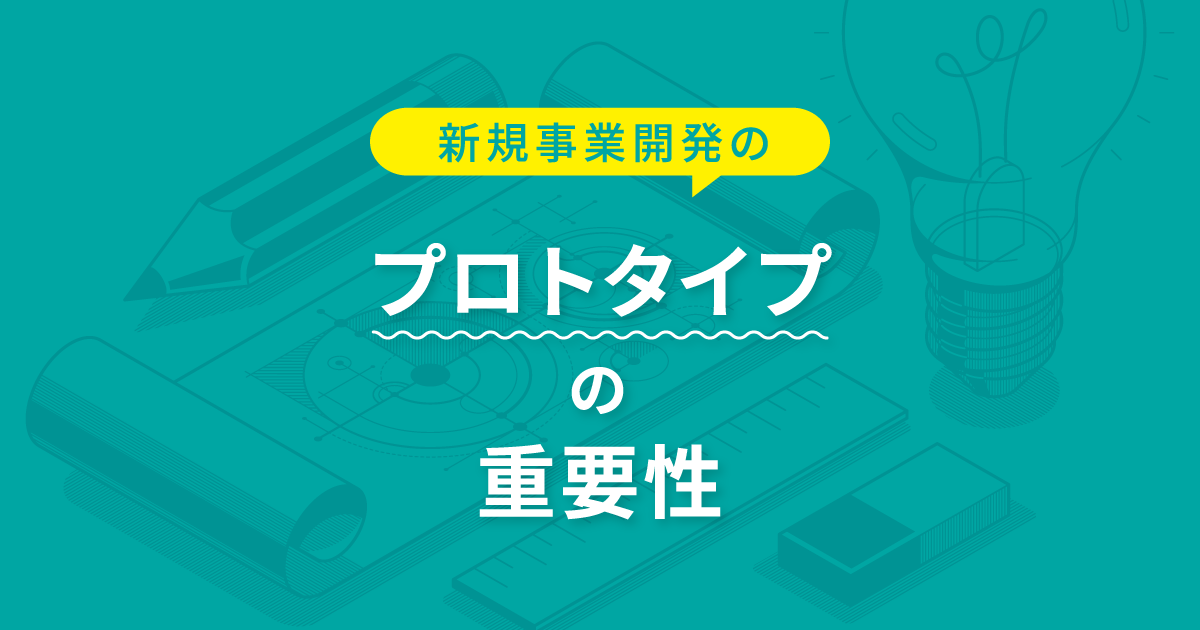
プロトタイプとは「アイデアの試作品」のことを指し、主にアイデア仮説を検証するときに活用するツールです。新規事業創出を行う上で失敗のリスクを減らし、認識齟齬を防ぐためには、企画フェーズの早い段階からプロトタイプを用いて仮説を検証することが大切です。
しかし、「完成度の低い試作品を作ってお客様に当てることに意味があるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実際、製造業のお客様向けにサービスデザインのワークショップや実務支援をしていると、このような疑問の声をあげる方が多いです。
本記事は、早期にプロトタイプをつくって活用することの重要性や、プロトタイプの種類、活用事例などを解説します。最後に、初期段階のプロトタイプ活用事例もご紹介します。
この記事におすすめな方
・新規事業を企画・担当している方
・プロトタイプを用いた早期仮説検証が必要か疑問に思っている方
プロトタイプとは
「プロトタイプ」とはアイデアの仮説を検証するために、ユーザーが理解しやすい形で言語や図、ツールなどを使ってつくられた「アイデアの試作品」のことを指します。
製造業において試作品(プロトタイプ)は、技術的課題とデザイン面の課題を発見するために作られるものとして馴染みがあると思います。しかし、新規事業創出においてプロトタイプを作る目的は、早い段階から失敗のリスクを減らすことと、関係者間での認識齟齬を防ぐことにあります。
市場の変化が早く、ユーザーのニーズが高度化・複雑化している現代において、ユーザーの課題解決につながる製品・サービス開発を行うためには、アイデア企画段階から短時間で、必要最小限のプロトタイプをつくり、繰り返し検証するプロセスを組み込むことが重要です。
早期からプロトタイプを活用することの重要性
❶ アイデアを早期に改善できる
従来のウォーターフォール型開発は企画、研究開発、生産、販売という工程でものづくりを行い、ユーザーから初めてフィードバックを受けるタイミングは製品・サービスを市場に出してからとなります。
しかし、多くの製造業の場合、市場に出すまでに2〜3年ほどかかってしまうため、その間にユーザーのニーズが変化していたり、他社が先に類似製品を発表してたりしてしまうことで、つくった製品が全然ユーザーに使われなかった…ということが多々あります。
ユーザーの課題とマッチしていない製品・サービスとなっている可能性に気づくのが遅れれれば遅れるほど、手戻りのコストは大きくなってしまいます。
だからこそ、アイデアのコンセプトの初案が決まった段階からプロトタイプを用いて検証を行い、早期にユーザーからフィードバックを獲得し、製品・サービスアイデアに反映して失敗のリスクを下げることが重要となります。
❷ 関係者間の認識ズレを防ぐことができる
「口頭や文章でアイデアを共有していたが、いざ開発・リリースしたらユーザーだけでなく開発者や営業、経営層などと認識がずれており、手戻りのコストが大きくかかってしまった」というケースも非常に多く見受けられます。
料理のレシピを例にとってみるとわかりやすいかと思います。
お菓子作りのレシピにはよく、このような文言が書かれていますが、みなさんはどのように作れば良いか想像できますか?
小麦粉をふるいにかけながら加えたあと、さっくり混ぜます。
文字だけでは、何を使って、どのように手を動かせば良いのかわからない人が多いのではないでしょうか。
しかし、写真や動画などを添えてあげることで、やるべきことの解像度をあげることができますね。
上記の例ではお菓子づくりの中のひとつの操作を切り取っていますが、新規事業で創出するアイデアの場合は、まだ誰も体験したことのないアイデアであることが多いため、より人によって解釈がバラバラになりがちです。
だからこそ、プロトタイプという言語だけでなく視覚的にアイデアを理解できる・体験できるツールを用意することで、相手のアイデアに対する理解度を深め、認識齟齬を防ぐことが重要です。
初期段階でつくるプロトタイプの種類
それでは、初期段階でどのようなプロトタイプを作れば効果的なのかが気になりますよね。
初期段階ではとにかく簡単なツールを用いて、できるだけ早く、必要最小限のプロトタイプを作成することがポイントです。その中でも、特に作成する頻度が多い3つのアウトプットをご紹介します。
ストーリーボード
文章と画像やイラストを使って、4コマ漫画風にユーザーの状況や課題、サービスの概要、提供価値を表現するアウトプットです。
パワーポイントやCanvaなどのツールを使い、簡単かつ数時間で作成することのできるプロトタイプであるのが特徴です。
サービス説明パンフレット
実際のサービスパンフレットのように、1枚の用紙でサービスの特徴や内容を具体的に伝えるアウトプットです。
ストーリーボードと比較すると、作成にかかる時間は増加しますが、サービスの特徴や利用イメージをより詳細に伝えることができるので、相手のアイデアに対する解像度を上げることができるのが特徴です。
サービス説明動画
1〜3分程度の動画で、サービスの利用イメージをより具体的に伝えるアウトプットです。
上記2つのアウトプットと比較すると、アニメーションを作成するコストが増えるため制作時間は増加しますが、相手のサービスの利用方法をより詳細にイメージしてもらうことができるのが特徴です。
製造業におけるプロトタイプの活用事例
早期からプロトタイプを活用しているお客様の事例をご紹介します。
医療機器メーカー様
「営業やカスタマーサポートセンターから得たお客様の改善要望を取り入れて製品を開発したものの、いざリリースしたらあまり使われない」という課題を抱えていました。
また、今まで口頭と文章だけでアイデアのイメージを共有していたため、企画・開発者間でも製品のイメージに対して認識齟齬が発生していました。
そこで、サービスデザインの手法を取り入れ新規事業創出活動を行うプロセスに導入し、アイデアの企画段階からストーリーボード形式のプロトタイプを用いてユーザー課題やアイデアの仮説検証を行うプロセスに変更。
チーム全員で意見を出し合いながらまずはストーリーボード形式のプロトタイプを作ることで、アイデアの概要・提供価値・利用方法について認識齟齬が発生している部分を明らかにし、内容をすり合わせることに繋がりました。
さらに、社内有識者向けのインタビューにおいてはサービスの利用イメージを正しく伝えることができ、そもそもの課題の認識がずれていることや、アイデアの何がユーザーの働く環境にマッチしていないのかといった有益な意見を聴き出すことができました。
その後も、開発者とのイメージ共有にプロトタイプを活用し、早期リスク低減・認識齟齬防止の活動を続けております。
自動車メーカー様
シニア向けに「新たな移動手段」を提供するアイデアを企画するプロジェクトにおいて、段階的にアイデアの仮説検証を行なった事例です。
最初のコンセプトレベルの検証では、ストーリーボードを用いて検証を行ないました。ユーザーの現状や課題についてのフィードバックは収集できるものの、サービスに対しては「どんな風に使うのかわからないから何とも言えない…….」と回答される方が多くいました。
そこで、次のステップではサービスの特徴と利用の流れを具体化した上で、パンフレット形式でよりサービスの内容をイメージできる形にしてユーザー検証を行いました。ストーリーボードでは収集できなかったサービスに対するフィードバックを多く収集することができました。
最後に、フィードバックを踏まえ利用の流れを改善し、動画形式でサービスを擬似体験できる環境を用意し、ユーザー検証を行いました。
上記の流れで、ユーザーだけでなくチーム内でのアイデアの解像度を高めていくことで、短期間で確度の高いアイデア創出に繋がりました。
まとめ:プロトタイプは「学習のための投資」
製造業において、プロトタイプは単なる「試作品」ではなく、「学習のための投資」と捉えるべきです。
完成品に近いプロトタイプでなくても、アイデア仮説検証の目的・目標を明確にし、プロトタイプを用いてユーザーからフィードバックを得ることで、貴重な学びを得ることができます。特に、顧客課題起点の新規事業創出においては、早期かつ繰り返し検証を行なってアイデアの解像度を高めていくことが成功の鍵となります。
製造業の強みである高い技術力に、プロトタイプを活用した高速で検証する文化を組み合わせることで、市場のニーズに的確に応える製品やサービスを生み出すことが可能になるでしょう。「作って終わり」ではなく、「作って学び、改善する」サイクルを回し続けることが、これからの製造業に求められる姿勢だと考えます。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。